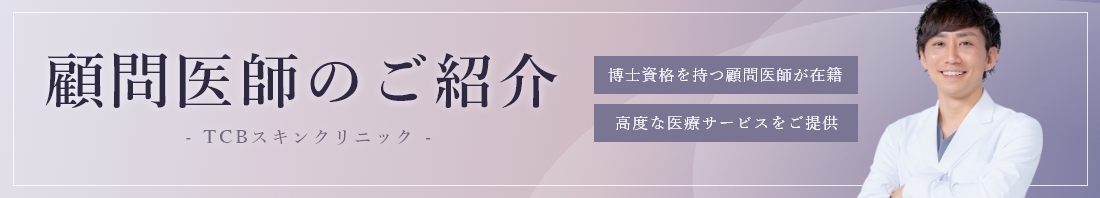投稿日:2025年02月13日

くり抜き法では根深いほくろの除去が可能ですが、傷跡はしばらく残ります。このコラムでは、くり抜き法の傷跡はいつまで残るのか解説し、傷跡が消えない場合の対処法も紹介します。ほくろの傷跡をきれいに治すには、治療後の過ごし方・ケア方法やクリニック選びも大切です。くり抜き法でほくろの除去を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
くり抜き法でほくろ除去後の傷跡が目立たなくなるまでの期間
くり抜き法でほくろを除去した場合、傷跡が目立たなくなるまで3~6ヶ月程度かかることが一般的です。
くり抜き法とは、メスでほくろをくり抜いて除去する方法です。くり抜き法は、基本的に手術後は縫合せずに、軟膏とテープを使って傷口を保護します。1センチ程度の大きさのほくろをくり抜いた場合は、すぼめるように縫合する場合もあります。まれに傷跡が盛り上がってしまったり、逆にへこんでしまったりする可能性もあります。
また、治療後は傷以外にも、腫れや赤み、かゆみなどの症状が生じる場合がありますが、2週間程度で徐々に落ち着きます。
ほくろ除去後の傷跡が消えない場合の対処法
ほくろを除去した傷跡がきれいに治るのか、不安に思う方も少なくありません。傷の治り方には個人差があり、経過を見ながら適切な対処をする必要があります。ただし、傷が治るまでにはある程度の期間が必要です。以下では、ほくろ除去後の傷跡が治らない場合の対処法を、治療後に経過した期間と合わせて紹介します。
治療から6ヶ月程度は様子を見る
治療から6ヶ月程度は、ほくろを除去した傷跡が消えなくても様子を見てください。
くり抜き法は傷跡が治るまで、時間がかかる場合がほとんどです。治療して6ヶ月以内であれば、まだ傷が治る途中の可能性も少なくありません。アフターケアを継続し、ダメージを避けながら経過を見ることが大切です。
また、傷跡が赤みのある盛り上がりとして残ることもあります。盛り上がりのある傷跡も、3~6ヶ月程度で徐々に治ることが一般的です。しかし、6ヶ月を過ぎても改善しない場合はケロイドの可能性があるため、早めの受診をおすすめします。
6ヶ月以上傷跡が残る場合はクリニックに相談する
治療から6ヶ月以上経っても傷跡が目立つ場合は、医療機関に相談してください。6ヶ月以上経つと傷の治りはある程度進行しており、時間の経過によってはそれ以上改善されない可能性があるためです。
治療を受けた医療機関に不安や不満がある場合は、別の医療機関で助言を受けるセカンドオピニオンを検討してもよいでしょう。担当医にセカンドオピニオンを受けたい旨を相談することで、紹介状を作成してもらえる場合があります。担当医と別の医療機関との間で治療に関する情報が共有されるため、やり取りがスムーズです。別の医療機関で治療を受けたい場合は、セカンドオピニオンを受けてみることをおすすめします。
ほくろ除去後に傷跡を残さないためのポイント
ほくろの除去後に、傷跡が残らないように治すためのポイントは以下の通りです。
- 自分でほくろ除去を行わない
- 治療後のアフターケアを欠かさず行う
自分でほくろ除去を行わない
ほくろの除去は自分で行わず、医療機関で除去することをおすすめします。はさみやカッターを使って自分でほくろを切ると、痛みを伴います。加えて、傷口から細菌が入って炎症や感染症を起こしてしまうリスクも少なくありません。傷跡がへこみやケロイドとなり、ほくろは除去できても傷跡が目立ってしまう可能性もあります。
また、市販のほくろ除去クリームは、皮膚を溶かすことでほくろを剥がす製品です。火傷や炎症を引き起こす可能性があるため、使わないようにしてください。
自分でほくろを除去するのに失敗してしまうと、医療機関の受診が必要となり、傷跡が治るまでに余分な時間や費用がかかることもあります。
さらに、ほくろのなかには、悪性のものもあります。ほくろが悪性かどうかについては、医師の判断が必要です。ほくろが悪性だった場合、自分での除去は症状の悪化につながる可能性があります。ほくろの状態に合った方法で除去するためにも、自分での除去は行わず、医療機関で相談しましょう。
治療後のアフターケアを欠かさず行う
治療後の過ごし方やケアの方法は、患部の回復に大きく影響を及ぼします。ほくろ除去後のアフターケアに関するポイントは、以下の通りです。
- 紫外線対策を行う
- 患部を刺激しない
- 医師の指示に従って軟膏や保護シールなどを使う
- 治療後にテーピングを行う
紫外線対策を行う
ほくろを除去した部分は紫外線のダメージを受けやすいため、紫外線対策をしましょう。紫外線の刺激によって、色素沈着やほくろの再発につながる場合があります。
具体的な対策方法には、以下があげられます。
- 日焼け止めを塗る
- 日傘や長袖の衣服で患部に直接紫外線が当たらないようにする
- なるべく日差しを避けて過ごす
肌に負担をかけないよう、低刺激の日焼け止めを使いましょう。SPF30程度の日常的に使える日焼け止めで構いません。肌への刺激の強い「紫外線吸収剤」は避け、「紫外線散乱剤」を選んでください。
「日焼け止めを患部に塗ることに抵抗がある」という方は、日傘や長袖の衣服で物理的に紫外線を当てないという方法もあります。ただし、ほくろを除去した患部に衣服が触れることも刺激の1つのため、注意が必要です。
患部を刺激しない
患部を触ったり、かさぶたを剥がしたりしないようにしてください。患部を刺激すると細菌が入り、傷が悪化することで傷跡が残りやすくなります。
ほくろの傷跡が気になっても、患部を無意識に触らないように気をつけましょう。かさぶたは傷が治ることで自然に剥がれ落ちるため、無理に剥がすことは禁物です。
医師の指示に従って軟膏や保護シールなどを使う
治療後は医師の指示に従い、処方された軟膏や保護シールでケアしましょう。軟膏や保護シールを使うことで、傷口を乾燥や炎症から守れます。保護シールは、服がこすれることによる刺激を減らすとともに、紫外線対策にも効果的です。
ほくろ除去を受けるクリニックの選び方
気になるほくろを除去するには、クリニック選びが大切です。クリニック選びで後悔しないために気をつけたいポイントは、以下の通りです。
- 症例や実績
- アフターケアや保証制度があるか
- 医師のカウンセリングやコミュニケーションが丁寧か
症例や実績
ほくろの除去は、医師の技術が大きく影響する治療です。クリニックにおける治療の症例数や実績は、さまざまな治療に対応してきた経験の豊富さを示す指標の1つとなります。
ただし、治療の質は症例数だけで決まるわけではないため、他の要素も考慮しながらクリニックを選ぶことが重要です。
アフターケアや保証制度があるか
治療後のケアや保証制度があるクリニックを選ぶと、万が一の際も安心です。
クリニックによっては、無料で再治療のできる期間を設定している場合があります。治療を受ける前に、アフターケアや保証制度について確認しておくことが大切です。
医師のカウンセリングやコミュニケーションが丁寧か
カウンセリングやコミュニケーションの面で安心できるクリニックを選びましょう。
傷跡が残ったり再発したりした場合は長期間通院することになるため、良好な関係を継続できるクリニックであることが重要です。
まとめ
ほくろをくり抜き法で除去した場合は、傷跡が治るまで3~6ヶ月程度かかることが一般的です。ただし、傷跡の治り方には個人差があり、患部の大きさによっても治るまでの期間は異なります。6ヶ月程度は様子を見ながら、医師の指示に従い患部を刺激しないようにケアしましょう。6ヶ月以上経過しても傷跡がきれいにならない場合は、再度受診することをおすすめします。
TCBスキンクリニックでは、さまざまなほくろ治療をご用意しています。ほくろ除去を検討している方はお気軽にTCBスキンクリニックの無料カウンセリングまでお越しください。無料カウンセリングにて、患者様一人ひとりに適した治療方法をご提案します。
本ページの監修医師
TCBスキンクリニックでは、しわやたるみを改善するエイジングケア治療、理想のフェイスラインにこだわった小顔治療、メスを使わない身体への負担が少ないプチ整形など、さまざまなメニューをご用意しております。患者様がリラックスしてご相談いただける環境を整え、丁寧なカウンセリングを通じて一人ひとりに適したプランをご提案いたします。「顔の印象を変えたい」「理想の見た目に近づきたい」など、治療に関するご要望がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。皆様のご来院をお待ちしております。
【新宿東口院】

経歴
- 東京女子医科大学医学部 卒業
- 順天堂大学附属順天堂医院 皮膚科
- 越谷市立病院 皮膚科
- 東京曳舟病院 皮膚科
- 同愛会病院 皮膚科
- 東京中央美容外科 新宿東口院 副院長
- 東京中央美容外科 渋谷西口院 院長
- 東京中央美容外科 秋葉原院 院長
- 東京中央美容外科 新宿東口院 院長
備考
- 日本皮膚科学会 正会員
- 日本医師会 認定産業医
- 日本美容医療学会(JAPSA) 会員



 シミ治療・そばかす消し
シミ治療・そばかす消し くすみ肌改善・美白治療
くすみ肌改善・美白治療 クマ
クマ 肝斑(かんぱん)治療
肝斑(かんぱん)治療 毛穴治療(黒ずみ・開き)
毛穴治療(黒ずみ・開き) ニキビ治療
ニキビ治療 ニキビ跡治療
ニキビ跡治療 肌診断「ネオヴォワール」
肌診断「ネオヴォワール」 角栓除去
角栓除去 ほくろ除去・いぼ除去
ほくろ除去・いぼ除去 シワ取り・ほうれい線治療
シワ取り・ほうれい線治療 たるみ治療
たるみ治療 若返り・エイジングケア
若返り・エイジングケア ヒアルロン酸注射(注入)
ヒアルロン酸注射(注入) ボトックス注射
ボトックス注射 小顔治療(注射・ハイフ・糸リフト)
小顔治療(注射・ハイフ・糸リフト) プチ整形(注射・切らない整形)
プチ整形(注射・切らない整形) 二重まぶた
二重まぶた ワキガ・多汗症
ワキガ・多汗症 医療ダイエット
医療ダイエット 肩こり
肩こり 医療レーザー脱毛
医療レーザー脱毛 小鼻縮小術(鼻翼縮小)
小鼻縮小術(鼻翼縮小) タトゥー除去・ケロイド治療
タトゥー除去・ケロイド治療 美容内服薬・外用薬
美容内服薬・外用薬 サプリメント
サプリメント 糸リフト(スレッドリフト)
糸リフト(スレッドリフト)