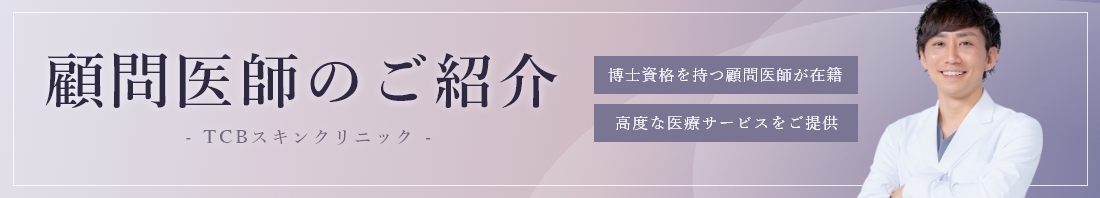投稿日:2025年02月13日

「ほくろ除去後にケロイドができた」「ケロイドが1年以上治らない」などのお悩みはありませんか?
ほくろ除去後の傷は、時間の経過とともに目立たなくなっていきますが、体質によってはケロイド状の傷跡が残ってしまう場合があります。
今回のコラムでは、ほくろ除去でできたケロイドの治し方や、傷跡を残さないための対策方法などについてご紹介します。
ほくろ除去後にできる傷跡の種類
ほくろ除去後の傷は、ダウンタイム中に徐々に改善する場合がほとんどです。しかし、炎症が悪化すると、傷跡が残る場合があります。
傷跡として残る可能性があるものには、ケロイド、色素沈着、凹みなどがあげられます。
ケロイド
ケロイドとは、皮膚の真皮で炎症が続くことで発生する赤く盛り上がった瘢痕です。
ほくろ除去後、まれに患部が赤く盛り上がる場合があります。赤みや盛り上がりが目立たなくなるまでの期間には個人差がありますが、通常は3~6ヶ月程度で徐々に落ち着きます。
ただし、6ヶ月以上経過しても症状が改善しない場合は、ケロイドや肥厚性瘢痕の可能性があるため注意が必要です。
色素沈着
ほくろ除去後の肌は炎症を起こしやすく、色素細胞の活性化によってメラニン色素が生成されるため、シミのような「炎症後色素沈着」が生じる場合があります。炎症後色素沈着は一時的なもので、肌が正常な状態に戻ると自然に消える場合がほとんどです。
しかし、6ヶ月以上経過しても消えない場合は、自己判断せずに医療機関を受診するようにしてください。
凹み
ほくろを取る際に患部を深く削りすぎると、皮膚の再生が追いつかず、治療後に皮膚が凹む可能性があります。また、切開を伴う手術で縫合が丁寧でない場合も、皮膚が凹むリスクがあります。小さな凹みは3~6ヶ月程度で治癒することがありますが、大きな凹みは完全に消えない場合もあるため、注意が必要です。
ケロイドが消えない場合の治し方は?
ほくろ除去で生じた色素沈着や凹みは自然治癒することがありますが、ケロイドができた場合、自然に治る可能性はほとんどありません。
ケロイドを治すためには、美容皮膚科や医療機関での治療が必要です。効果的な治療方法には、レーザー治療やステロイド注射、圧迫療法などがあります。
ケロイドを放置すると、大きくなったり、固くなったりする場合があるため、早めに医療機関を受診することが大切です。
ほくろ除去で傷跡が残らない対策方法
ほくろ除去後に傷跡を残さないためには、セルフケアとして以下の対策を行うように心がけてください。
かさぶたを剥がさない
ほくろ除去後、治療部位にかさぶたができる場合がありますが、通常は1週間程度で自然に剥がれ落ちます。かさぶたは、傷口が治癒する過程で形成されます。かさぶたを無理やり剥がすことで、患部がきれいに治らない可能性があるため注意が必要です。また、かさぶたを剥がしてしまうと、紫外線や乾燥などのダメージを受けやすくなり、炎症や色素沈着を引き起こすリスクが高まります。
保護テープを貼る期間を守る
ほくろ除去後は、傷が完全に閉じていないため、患部に保護テープを最低10日間貼り続ける必要があります。保護テープは、患部への刺激を軽減し、雑菌の侵入を防ぐ役割があります。症状が落ち着いたと感じても、自己判断で剥がさず、指定された期間を守るようにしてください。
紫外線対策を徹底する
ほくろ除去後は、肌のバリア機能が低下しているため、紫外線の影響を受けやすく、色素沈着を引き起こす可能性があります。色素沈着を防ぐためには、治療後1ヶ月程度、日焼け止めや日傘を活用し、紫外線対策を徹底するように心がけてください。
また、大量の紫外線を浴びると、ほくろの原因となるメラニンが過剰に生成され、新しいほくろができる可能性があります。ほくろを増やさないためにも、日頃から紫外線対策を心がけることが大切です。
美容皮膚科でのほくろ除去方法
顔や身体の目立つ部位のほくろを美容目的できれいに除去したい場合は、美容皮膚科での治療が効果的です。
自分でほくろを取る方法として、ほくろ除去クリームや針、ナイフなどがありますが、傷跡や火傷、皮膚疾患を引き起こすリスクが伴います。また、自己処理では限界があり、完全に取り除くことは困難です。
美容皮膚科でほくろを除去する方法には、「レーザー治療」「電気メスによる表面分解法」「切開法」「くり抜き法」などがあります。
レーザー治療
レーザー治療は、CO2レーザー(炭酸ガスレーザー)、ピコレーザー、QスイッチYAGレーザーを使用してほくろを除去する方法です。
CO2レーザーは、ほくろのある部位にレーザーを照射すると、水分と反応して熱エネルギーが発生し、ほくろの組織をピンポイントで蒸散させます。短時間でほくろを除去することが可能です。ピコレーザーやQスイッチYAGレーザーによる治療は、レーザーでほくろの原因であるメラニン色素を破壊して除去します。
治療後には赤みや腫れが生じる場合がありますが、メスを使用しないため傷跡がほとんど残らない点が特徴です。
電気メスによる表面分解法
表面分解法とは、電気メスの熱を利用してほくろの表面を削り取る治療方法です。ほくろの細胞を焼灼するため、治療後に赤みや皮膚が凹む可能性がありますが、通常は3~6ヶ月程度で落ち着きます。
表面分解法は、治療と同時に止血を行うため、出血がほとんどない点が特徴です。また、医師が患者様のほくろの大きさや膨らみを確認しながら治療を進めるため、瘢痕化のリスクを抑えられます。
切開法
切開法とは、ほくろをメスで切り取り、周囲の皮膚を縫合する手術です。ほくろの周辺組織を切除するため、大きなほくろを根本から除去できます。
縫合を行うため、抜糸後に傷跡が残る可能性がありますが、時間の経過とともに目立たなくなる場合がほとんどです。また、再発のリスクが低く、手術後の腫れが抑えられる点が特徴です。
くり抜き法
くり抜き法とは、メスを使ってほくろを円形にくり抜き、除去する手術方法です。ほくろの根元をしっかりと取り除くため、再発のリスクが低い点が特徴です。ほくろの大きさによっては、手術後に縫合を行わず、軟膏とテープで傷口を保護するため、身体への負担を抑えながら除去が可能です。
治療後に赤みや痛み、傷跡などが残る場合がありますが、時間の経過とともに落ち着きます。
ほくろ除去で後悔しないためのクリニックの選び方
ほくろ除去で後悔しないためには、クリニック選びが重要です。選ぶ際のポイントは以下のとおりです。
- 丁寧なカウンセリングの実施
- アフターケアや保証制度の有無
- クリニックの症例数や実績の豊富さ
- 治療方法の多様性
症例数の多さは、さまざまな治療に対応してきた経験の豊富さを示す指標の1つとなります。ただし、治療の質は症例数だけで決まるわけではありません。医師の技術や経験、患者様の状態に合わせた治療方針の決定なども、クリニックを選ぶ際の重要な要素です。
TCBスキンクリニックでは、患者様一人ひとりの状態に合わせ、適切な治療方法をご提案します。
まとめ
ほくろを取った後、ケロイドや色素沈着、凹みなどの傷跡ができる場合があります。傷跡は通常、3~6ヶ月程度で徐々に落ち着きますが、なかなか治らない場合は医療機関での治療が必要です。
ほくろ除去後に傷跡を残さないためには、紫外線や摩擦などの外部刺激から患部を守り、かさぶたや保護テープを剥がさないことが重要です。また、傷跡を残さないためにはクリニック選びも大切となります。
TCBスキンクリニックでは、さまざまなほくろ治療をご用意しています。ほくろ除去を希望する方は、お気軽にご相談ください。無料カウンセリングを承っています。
本ページの監修医師
TCBスキンクリニックでは、しわやたるみを改善するエイジングケア治療、理想のフェイスラインにこだわった小顔治療、メスを使わない身体への負担が少ないプチ整形など、さまざまなメニューをご用意しております。患者様がリラックスしてご相談いただける環境を整え、丁寧なカウンセリングを通じて一人ひとりに適したプランをご提案いたします。「顔の印象を変えたい」「理想の見た目に近づきたい」など、治療に関するご要望がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。皆様のご来院をお待ちしております。
【新宿東口院】

経歴
- 東京女子医科大学医学部 卒業
- 順天堂大学附属順天堂医院 皮膚科
- 越谷市立病院 皮膚科
- 東京曳舟病院 皮膚科
- 同愛会病院 皮膚科
- 東京中央美容外科 新宿東口院 副院長
- 東京中央美容外科 渋谷西口院 院長
- 東京中央美容外科 秋葉原院 院長
- 東京中央美容外科 新宿東口院 院長
備考
- 日本皮膚科学会 正会員
- 日本医師会 認定産業医
- 日本美容医療学会(JAPSA) 会員



 シミ治療・そばかす消し
シミ治療・そばかす消し くすみ肌改善・美白治療
くすみ肌改善・美白治療 クマ
クマ 肝斑(かんぱん)治療
肝斑(かんぱん)治療 毛穴治療(黒ずみ・開き)
毛穴治療(黒ずみ・開き) ニキビ治療
ニキビ治療 ニキビ跡治療
ニキビ跡治療 肌診断「ネオヴォワール」
肌診断「ネオヴォワール」 角栓除去
角栓除去 ほくろ除去・いぼ除去
ほくろ除去・いぼ除去 シワ取り・ほうれい線治療
シワ取り・ほうれい線治療 たるみ治療
たるみ治療 若返り・エイジングケア
若返り・エイジングケア ヒアルロン酸注射(注入)
ヒアルロン酸注射(注入) ボトックス注射
ボトックス注射 小顔治療(注射・ハイフ・糸リフト)
小顔治療(注射・ハイフ・糸リフト) プチ整形(注射・切らない整形)
プチ整形(注射・切らない整形) 二重まぶた
二重まぶた ワキガ・多汗症
ワキガ・多汗症 医療ダイエット
医療ダイエット 肩こり
肩こり 医療レーザー脱毛
医療レーザー脱毛 小鼻縮小術(鼻翼縮小)
小鼻縮小術(鼻翼縮小) タトゥー除去・ケロイド治療
タトゥー除去・ケロイド治療 美容内服薬・外用薬
美容内服薬・外用薬 サプリメント
サプリメント 糸リフト(スレッドリフト)
糸リフト(スレッドリフト)