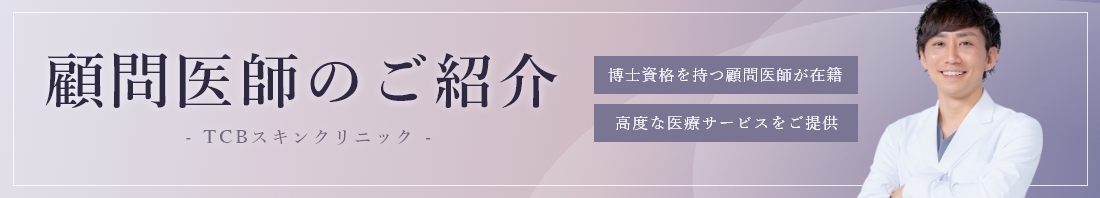投稿日:2025年08月05日

ほくろが痛いと感じた経験はありませんか? ほくろは皮膚の一部であり、通常は痛みを感じることはありません。しかし、突然痛みを伴うようになると、不安に感じる方も多いでしょう。痛みを伴うほくろには、何らかの変化や異常が起きている可能性があります。
本記事では、ほくろの痛みが発生する原因と対処法を詳しく解説します。
ほくろが痛い原因は?
ほくろが痛い原因には、いくつかの要因が考えられます。主な原因た特徴を詳しく説明します。
ほくろの炎症
ほくろが赤く腫れて痛みを伴う場合、炎症が原因となっている可能性があります。長期間炎症が続く場合、周囲の皮膚も赤く腫れ、膿が発生する恐れがあるでしょう。炎症が起こる理由としては、日常的な摩擦や衣服の圧力、紫外線によるダメージなどが考えられます。特に日焼けをしている場合や、衣服が直接ほくろに触れている場所では、炎症が起こりやすいです。
外的刺激
衣類やアクセサリー、スポーツ、日常生活での摩擦など、外的な刺激によってほくろが痛む時があります。特に体の動きや圧力による摩擦を受けやすい場所にあるほくろは、痛みが強くなる場合があります。ほくろの位置によっては、髪を洗う時や衣服の着脱時、寝ている間の枕との接触などが原因で痛みを引き起こします。
ほくろの変化や成長
ほくろが急に大きくなったり形が変わったりすると、周辺の皮膚に痛みを感じる場合があります。皮膚内で細胞が増殖している恐れがあり、痛みの強さやほくろの大きさ、色の変化などの観察が重要です。また、色むらがある、形が不規則になるといった症状も異常のサインと考えられます。
皮膚がんの初期症状の可能性
ほくろが痛む場合、最も注意すべきなのは、皮膚がんの一種でメラノーマとも呼ばれる悪性黒色腫の初期症状です。左右非対称の形や色むら、大きさが6ミリ以上などの症状が見られます。人種差があり、白人に多く見られる病気ですが、日本人でも毎年10万人あたり2人未満が罹患しています。病気の進行が非常に早く命に関わる病気のため、少しでも異常を感じた場合は早急に医療機関を受診してください。
ほくろに痛みを感じた時の対応
痛みが軽度であれば、まずは冷たいタオルや氷でほくろを冷やし痛みを和らげましょう。冷却することで、炎症を抑える効果があります。ただし、強くこすったり圧迫したりすることは避けてください。
また、痛みが強くなる前に必要に応じて医療機関を受診しましょう。冷却は一時的な対処法に過ぎません。痛みが続いたり異常が見られる場合は、自己判断で行動せず必ず医師に相談してください。
医療機関での治療
痛みが続く、腫れが引かない、出血が見られる、ほくろの色や形が変化している場合など、ほくろが痛む原因が不明な場合や痛みがひどい場合は、早期に医師の診断を受けましょう。いち早く異常を発見し治療を開始することで、深刻な病気を予防できます。医師は視診や必要に応じて組織検査を行い、ほくろの状態を確認します。これにより、痛みの原因が悪性かどうか、早期治療が必要かどうかが明確になります。痛みが続く場合は、治療方法を医師と相談しましょう。
ほくろが悪性の場合、早期の治療が必要です。除去後は傷口の治癒を確認するため、定期的な通院が必要な場合があります。治療後は傷口が感染しないよう注意し、医師の指示に従ってケアを行ってください。
痛みを予防するための日常的なケア
ほくろの痛みを予防するためには、日常的なケアが重要です。ほくろに外的な刺激を与えないよう心がけ、紫外線対策を十分に行ってください。
皮膚への刺激を減らす
皮膚への刺激を減らすことで、痛みを予防できます。特に、衣服やアクセサリーがほくろに直接触れないように注意してください。また、ほくろを傷つけたり頻繁に触れたりすると、大きくなったり悪性化する可能性があるため、刺激を与えないようにしましょう。
十分な紫外線対策
紫外線はほくろの変化を引き起こす原因となるため、日焼け止めをしっかり塗ることが重要です。また、日中外出する際は、帽子やサングラスで紫外線を遮るようにしましょう。
まとめ
ほくろに痛みを感じた場合、健康に対する警告信号である可能性があります。
通常、ほくろは痛みを伴わない良性の皮膚変化ですが、何らかの刺激や異常が加わった際に痛みを感じることがあります。たとえば、炎症や感染、または皮膚がんなどの重篤な疾患が背景にある場合も考えられます。異変を軽視して放置してしまうと、症状が進行し、治療が困難になるおそれがあります。場合によっては命に関わるリスクもあるため、「ただのほくろ」と自己判断せず、早めに医療機関を受診することが大切です。
特に、痛みが長引く、形や色に変化が見られる、急に大きくなった、出血やかさぶたを繰り返すなどの異常がある場合は、専門の医師による診察を受けてください。早期に適切な対処を行うことで、重篤な病気を未然に防ぐことができます。
本ページの監修医師
TCBスキンクリニックでは、しわやたるみを改善するエイジングケア治療、理想のフェイスラインにこだわった小顔治療、メスを使わない身体への負担が少ないプチ整形など、さまざまなメニューをご用意しております。患者様がリラックスしてご相談いただける環境を整え、丁寧なカウンセリングを通じて一人ひとりに適したプランをご提案いたします。「顔の印象を変えたい」「理想の見た目に近づきたい」など、治療に関するご要望がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。皆様のご来院をお待ちしております。
【新宿東口院】

経歴
- 東京女子医科大学医学部 卒業
- 順天堂大学附属順天堂医院 皮膚科
- 越谷市立病院 皮膚科
- 東京曳舟病院 皮膚科
- 同愛会病院 皮膚科
- 東京中央美容外科 新宿東口院 副院長
- 東京中央美容外科 渋谷西口院 院長
- 東京中央美容外科 秋葉原院 院長
- 東京中央美容外科 新宿東口院 院長
備考
- 日本皮膚科学会 正会員
- 日本医師会 認定産業医
- 日本美容医療学会(JAPSA) 会員



 シミ治療・そばかす消し
シミ治療・そばかす消し くすみ肌改善・美白治療
くすみ肌改善・美白治療 クマ
クマ 肝斑(かんぱん)治療
肝斑(かんぱん)治療 毛穴治療(黒ずみ・開き)
毛穴治療(黒ずみ・開き) ニキビ治療
ニキビ治療 ニキビ跡治療
ニキビ跡治療 肌診断「ネオヴォワール」
肌診断「ネオヴォワール」 角栓除去
角栓除去 ほくろ除去・いぼ除去
ほくろ除去・いぼ除去 シワ取り・ほうれい線治療
シワ取り・ほうれい線治療 たるみ治療
たるみ治療 若返り・エイジングケア
若返り・エイジングケア ヒアルロン酸注射(注入)
ヒアルロン酸注射(注入) ボトックス注射
ボトックス注射 小顔治療(注射・ハイフ・糸リフト)
小顔治療(注射・ハイフ・糸リフト) プチ整形(注射・切らない整形)
プチ整形(注射・切らない整形) 二重まぶた
二重まぶた ワキガ・多汗症
ワキガ・多汗症 医療ダイエット
医療ダイエット 肩こり
肩こり 医療レーザー脱毛
医療レーザー脱毛 小鼻縮小術(鼻翼縮小)
小鼻縮小術(鼻翼縮小) タトゥー除去・ケロイド治療
タトゥー除去・ケロイド治療 美容内服薬・外用薬
美容内服薬・外用薬 サプリメント
サプリメント 糸リフト(スレッドリフト)
糸リフト(スレッドリフト)